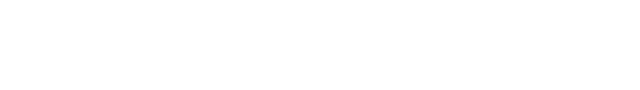運動器不安定症(MADS)について
高齢者を中心に、運動機能(筋力・骨・関節など)が低下して歩行時のふらつきや転倒が起こりやすい状態を指します。加齢や運動不足など様々な要因が重なって発症し、日常生活への支障だけでなく、要介護状態への移行リスクを高めることがあります。
1. 主な症状
歩行時のふらつき・バランス不良
足元が安定しないため、転倒しそうになる回数が増える
転倒リスクの増加
一度の転倒が骨折や寝たきりのきっかけになる場合もある
関節の痛み・骨の脆弱性
膝や腰などに痛みを感じやすく、軽微な外傷でも骨折しやすい
筋力や柔軟性の低下
太ももの筋肉や体幹の筋力が衰え、立ち上がりや移動動作が困難になる
2. 原因
加齢による筋力・骨密度の低下
加齢とともに運動器(筋肉・骨・関節)が変性し、支えにくくなる
運動不足や不適切な生活習慣
長期にわたる活動不足で筋肉や骨に刺激が少なく、弱りやすい
関節の変形や痛み(変形性関節症など)
痛みをかばって動かなくなることで、さらに筋力が落ちて悪循環に陥る
3. 診断のポイント
1. 日常生活自立度の評価
日本整形外科学会などが定める基準で、歩行やADL(食事や排泄などの日常動作)の状態をチェック
2. 開眼片脚起立テスト
両目を開けて片足立ちを維持できる時間が短い(15秒未満)とバランス能力の低下が疑われる
3. Timed Up and Goテスト(TUGテスト)
椅子から立ち上がり、3m先を回って戻るまでの時間が11秒以上かかると歩行機能の低下が考えられる
4. 治療と予防方法
進行を防ぎ、生活の質を維持するために、早めの対策が重要です。
リハビリテーション・運動療法
- 筋力トレーニング(下肢や体幹)、バランス訓練、ストレッチ
薬物療法
骨粗鬆症の予防や関節の痛みを抑える薬の使用
環境調整
家の中の段差解消や手すりの設置など、転倒リスクを減らす工夫
生活習慣の見直し
適度な運動を定期的に行い、食事などで骨や筋肉に必要な栄養をしっかり摂る
5. ロコモティブシンドローム(ロコモ)との関係
運動器の障害で要介護リスクが高まる状態を「ロコモ」と呼ぶ
運動器不安定症はロコモの中でも「移動機能が低下した状態」として位置づけられる
早期チェック・対策が重要
ロコチェックで日常生活の動作に困りごとがないか、定期的に確認すると効果的
加須市 栗橋駅にある「こばやし整形外科」
立ち上がりや歩行が不安定になったと感じたら、早めに対策を講じることが大切です。リハビリや生活環境の調整などで、転倒や要介護リスクを大きく減らせます。
加須市 栗橋駅にある「こばやし整形外科」は、一人ひとりの症状や生活スタイルに合わせた治療とサポートを行っています。お気軽にご相談ください。