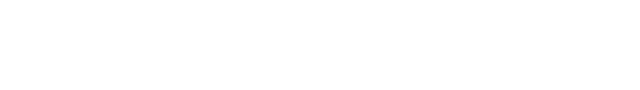足関節果部骨折(くるぶしの骨折)について
足首周辺にあるくるぶし(内果・外果)を含む骨が折れる状態を指し、足をひねったり転倒・落下などの強い外力で発生します。骨折が関節内に及ぶ場合、適切な整復・固定が行われないと将来的に変形性関節症へ進行するリスクがあり、早期診断と適切な治療が重要です。
1. 主な原因とメカニズム
足首に強い捻りや衝撃
スポーツ中の急な切り返しや着地、転倒で足首をねじった際に発生
交通事故や高所からの落下
体重がかかった状態で足首に大きな力が加わる
骨の弱化(骨粗鬆症など)
高齢者では骨強度の低下によって骨折しやすくなる
2. 症状の特徴
足首の激しい痛みと腫れ
骨折直後から強い痛みが走り、腫れや内出血が顕著
荷重不可・歩行困難
足を地面につけるだけで激痛が走り、まともに歩けない
くるぶし周辺の変形
外反、内反など足首の傾きが明確にわかる場合も
可動域の制限
足首を曲げ伸ばしするのが極めてつらい
3. 分類方法
1. Lauge-Hansen分類
足の位置と捻りの力が加わる方向に基づき骨折タイプを判定
2. Weber分類
- 腓骨の骨折部位の高さに基づいてA・B・Cタイプに区分
- 高度が上がるほど関節に近づき、重症度が増す
4. 診断と検査
問診と身体所見
受傷機転や痛みの場所、変形の有無を確認
画像検査(X線・CTなど)
骨折線の位置、関節内への延長、骨片のずれを把握
MRI(必要に応じて)
軟骨や靭帯損傷の併発を詳しく調べる
5. 治療方法
骨折の種類や重症度、ずれの大きさによって保存療法か手術療法を選択。
1. 保存療法(軽度またはずれの少ない骨折)
- ギプスやブーツ型装具で足首を固定し、自然癒合を促す
- 定期的にX線検査で骨癒合の進み具合を確認
2. 手術療法(複雑骨折・関節内骨折など重度の場合)
- 金属プレートやスクリューを用いて骨片を整復し固定
- 術後のリハビリで可動域回復と筋力強化を図る
6. リハビリテーションと予後
骨癒合後6週間前後からリハビリ開始
固定解除後、足首の可動域訓練や筋力回復トレーニングを行う
荷重練習の時期
手術や骨折の種類により異なるが、徐々に体重をかける練習を進める
将来的な合併症リスク
関節内骨折では変形性関節症のリスクが高まる場合もある
適切な治療とリハビリで多くの人が回復
治療の質とリハビリ次第で良好な機能回復が期待できる
加須市 栗橋駅にある「こばやし整形外科」
足首まわりに激痛や腫れがある場合、足関節果部骨折が疑われます。当院では、専門医がX線やCTなどで骨折の状態を正確に把握し、保存療法・手術療法・リハビリを含めた最適な治療プランをご提案いたします。早期治療で良好な回復を目指せますので、気になる症状があればお早めにご相談ください。